危険物は爆発しやすい物質や引火しやすい物質、人体に有害な物資など、さまざまな種類があります。危険物倉庫では、倉庫内でどの危険物をどんな方法で保管する必要があるのか法令で定められています。ここでは、消防庁が公開している『消防法令抜粋(消防法上の危険物の定義、試験方法など)』から6種類の「危険物」を中心に解説していきます。
酸化性固体は、それ自体は燃焼しないが、他の物質と触れると、その物質を強く酸化させる固体です。熱、衝撃、摩擦によって分解し、可燃物を激しく燃焼させる危険性があります。塩素酸塩類・過塩素酸塩類・無機過酸化物・亜塩素酸塩類・臭素酸塩類・硝酸塩類・よう素酸塩類・過マンガン酸塩類・重クロム酸塩類などの種類があります。
可燃性固体は、40度未満の比較的低温で着火しやすい固体です。燃焼が早く、消火が困難な性質があります。硫化りん・赤りん・硫黄・鉄粉・金属粉・マグネシウムなどがあり、工業製品の材料に使われているものが多いのが特徴です。
自然発火性物質及び禁水性物質とは、空気にさらされると自然発火する可能性がある固体や液体、または水に触れると発火したり、大量の可燃性ガスをおこす物質です。具体的には、ナトリウム・カリウム・アルキルリチウム・アルキルアルミニウム・黄りんなどをさします。
引火性液体は、20℃以上の環境で液状となる物質で、引火しやすい液体です。引火点250度未満のものと定義されています。具体的には、アルコール・石油・ガソリン・灯油・動物性油脂などです。比較的身近にあり、ごく少量保管する場合は普通の倉庫でもよい場合があります。
自己反応性物質とは、加熱や加水、衝撃などがきっかけで高熱を発したり爆発したりする物質のことです。有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・ニトロソ化合物・アゾ化合物 ・ジアゾ化合物・ヒドラジンの誘導体・ヒドロキシルアミン・ヒドロキシルアミン塩類などがあります。
酸化性液体は、その液体自身は燃えませんが、可燃物に混入すると、その可燃物の燃焼を加速度的に促進させる液体です。主な酸化性液体には、過塩素酸・ 過酸化水素・硝酸などがあります。
消防法による6種類の他に、「危険物の規制に関する政令」では糸、わら、ぼろ布や紙くず、かんな屑や綿花なども「燃えやすいもの」として「危険物」と解釈されています。保管する分量が多ければ規制の対象になることがあるので、「何が危険物か」知りたい場合は、危険物倉庫の建設実績を積んだ建設会社に相談することをおすすめします。
当サイトでは実績のあるメーカーをご紹介。
さらにその中で、多くの危険物倉庫建設を手掛けているメーカーに注目。
用途別にご紹介します。
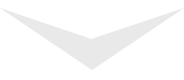

引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
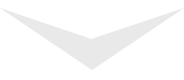

引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
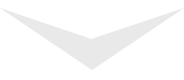

引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
【選定基準】
Googleにて「危険物倉庫建設」「危険物倉庫建築」と検索示された全メーカーのうち、危険物倉庫の事例がある、且つ公式サイトで倉庫全般をメインに事業を展開しているメーカー22社をピックアップ。実績のあるメーカーとして
・三和建設:自由設計のメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・太陽工業:テント倉庫メーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・ナガワ:ユニットハウスメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例の掲載をしている
を条件に3社をピックアップしています。