危険物を保管するための施設や倉庫を建設する際、敷地の広さや周辺との間隔などに注意しなければなりません。
このページでは、危険物倉庫建設に必要な「保有空地」について詳しく紹介します。
保有空地とは、ガソリン・灯油・油性塗料などの「危険物」を保管するための貯蔵所の周囲に設けられる空き地のことです。
貯蔵所は、たとえば倉庫のように屋根・壁・扉がついている建物が挙げられますが、安全に保管を続けるためには、貯蔵所のまわりに保有空地を設けなければなりません。
危険物は正しく取り扱わなければ火災やその他の災害に発展する可能性があるため、建物の周囲にも十分なスペースが必要になります。
スペースがない、または極端に狭いスペースしかない場合、危険物が何らかの理由で発火すると周辺の建物や自然に火が燃え移る可能性があるため、火災や延焼のリスクを抑えるという意味でも保有空地が重要な役割を果たします。
保有空地は、指定数量(危険物の種類ごとに定められた基準の数量)の何倍の量を貯蔵所や製造所に保管しているかによって、確保しなければならない保有空地の幅が異なります。また、その危険物を保管する建物が耐火構造である場合は、保有空地の幅を狭くすることができます。
「消防法」および「危険物の規制に関する政令」に基づいて規定された総務省令では、危険物の貯蔵について以下のように定められています。
| 区分 | 空地の幅 | |
|---|---|---|
| 当該建築物の壁・柱・床が耐火構造である場合 | 左欄以外の場合 | |
| 指定数量の倍数が5以下の屋内貯蔵所 | - | 0.5m以上 |
| 指定数量の倍数が5を超え10以下の屋内貯蔵所 | 1m以上 | 1.5m以上 |
| 指定数量の倍数が10を超え20以下の屋内貯蔵所 | 2m以上 | 3m以上 |
| 指定数量の倍数が0を超え50以下の屋内貯蔵所 | 3m以上 | 5m以上 |
| 指定数量の倍数が50を超え200以下の屋内貯蔵所所 | 5m以上 | 10m以上 |
| 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 | 10m以上 | 15m以上 |
一例として、アルコール類(第四類)の指定数量は400リットルと定められており、5以下の倍数(2000リットル以下)で耐火構造を有していない屋内貯蔵所に保管する際は、0.5m以上の幅を設けなくてはなりません。
保安距離を測定する方法は、地方自治体によってそれぞれ細かなルールが異なっています。一例として、沖縄県うるま市では以下のように定めています。
屋外の工作物と危険物流出防止のための囲い等の距離が相当開いている(概ね2m以上。)場合の保有空地は、当該囲い等から測定すること。ただし、ローリー充填所、屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の屋外に設置するポンプ設備等で、周囲の状況により安全性が確保されるものにあっては、充填口又は注入口(架構又は作業架台等を含む)その他地上に固定された機器・設備等の先端をもって、その起算点とすることができる。
引用元:うるま市役所「別記3 保有空地」(https://www.city.uruma.lg.jp/userfiles/U81/files/bekki3.pdf)
測定方法の詳細は地域ごとに異なるため、管轄する自治体へ確認してください。
当サイトでは実績のあるメーカーをご紹介。
さらにその中で、多くの危険物倉庫建設を手掛けているメーカーに注目。
用途別にご紹介します。
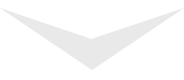

引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
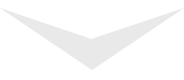

引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
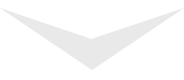

引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
【選定基準】
Googleにて「危険物倉庫建設」「危険物倉庫建築」と検索示された全メーカーのうち、危険物倉庫の事例がある、且つ公式サイトで倉庫全般をメインに事業を展開しているメーカー22社をピックアップ。実績のあるメーカーとして
・三和建設:自由設計のメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・太陽工業:テント倉庫メーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・ナガワ:ユニットハウスメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例の掲載をしている
を条件に3社をピックアップしています。