危険物倉庫は「都市計画法」「建築基準法」「消防法」「港湾法」などの法律で建設や運営を規制されています。危険物倉庫を建てる時に知っておくべき法律をまとめました。
都市計画法は、都市計画に必要な事項を定めている法律。具体的には「都市計画」「都市計画制限等」「都市計画事業」「都市施設等設備協定」があります。危険物倉庫は「都市計画」「都市計画制限等」などで、倉庫を建てる区域が規制されています。特に「用途地域」には注意が必要。土地によっては危険物倉庫を建てられない場合があります。
建築基準法は、国民の生命財産を守り、安全に暮らすことができるようにするために、建物や土地に対して定められたルール。規制対象になるのは建築物・建築物の敷地・設備・構造・用途などで、危険物倉庫に対しても、面積・高さ・建蔽率・容積率・保安空地など、厳しい規制が課せられています。
火災から国民の生命、身体、財産を守るために制定されているのが消防法です。
消防法では「火災を発生させる危険性が高い物質」「火災を拡大する危険性がある物質」「消火の困難な物質」を6種類に分類して「危険物」として指定。貯蔵する建物の規制や、危険物の取り扱い、運搬方法などについて、安全確保のための厳しい基準を設けています。
港湾区域や臨港地区、港湾工事の費用、開発保全航路などを定める港湾法。危険物倉庫は港湾法にも規制されています。危険物管理が必要なのは、輸出輸入などで船舶に積み込まれる「工業製品の材料としての危険物」と「船舶の燃料としての危険物」の2種類。船舶と危険物倉庫側の緊密な情報共有が大切です。
次の物質が「危険物」に指定されています。
市町村火災予防条例では、消防設備、火災警報装置、静電気の防止、配管、貯蔵容器・タンクなどの仕様に細かい規制が定められています。
危険物倉庫は、引火性・爆発性が高く、人体に有害な物質を保管するための倉庫なので、一般の倉庫とは違う仕様が必要になります。危険物倉庫建設実績が多い建設会社に相談してみてはいかがでしょうか。
「危険物」とはどんなもののことでしょうか?ここでは消防庁が定めた6種類の「危険物」の定義、具体的にどんなものが危険物にあたるのかを一覧にしました。危険物の種類によって、倉庫の仕様が異なりますので、チェックしてみてください。
倉庫で、危険物を管理するリスクには「火災」「爆発」「危険物の流出」などがあります。いずれも自社だけでなく隣接する施設や住民に被害が及ぶ災害となります。ここでは、危険物倉庫のリスクである「火災」について、消防白書のデータを元に解説しています。
「危険物倉庫と普通の倉庫の違いがよくわからない」とお悩みの方のために、危険物倉庫の定義や種類、危険物倉庫の建築や設置基準などの情報を集めました。低コストで危険物倉庫を建てるアイデアは必見です。
危険物倉庫建設は、従業員や近隣地域の安全を守るため行政の規制が厳しくなっており一般の倉庫を建てる時よりも手続きが煩雑です。ここでは危険物倉庫建設の流れを追っていきます。特に行政への認可申請のポイントは要チェックです。
当サイトでは実績のあるメーカーをご紹介。
さらにその中で、多くの危険物倉庫建設を手掛けているメーカーに注目。
用途別にご紹介します。
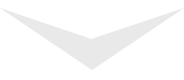

引用元:三和建設公式サイト https://risoko.jp/performance_k/prologis_reit/
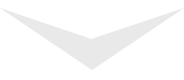

引用元:太陽工業公式サイト https://www.tentsouko.com/products/%e4%bc%b8%e7%b8%ae%e5%bc%8f%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%88%e5%80%89%e5%ba%ab/
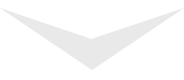

引用元:大和リース公式サイト https://www.daiwalease.co.jp/works/prefab/861
【選定基準】
Googleにて「危険物倉庫建設」「危険物倉庫建築」と検索示された全メーカーのうち、危険物倉庫の事例がある、且つ公式サイトで倉庫全般をメインに事業を展開しているメーカー22社をピックアップ。実績のあるメーカーとして
・三和建設:自由設計のメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・太陽工業:テント倉庫メーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例を掲載している
・ナガワ:ユニットハウスメーカーの中で最も多く危険物倉庫の事例の掲載をしている
を条件に3社をピックアップしています。